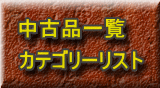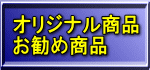オーディオ専門店エレックスは各種オーディオ機器を専門とするショップです。
 オーディオ専門店エレックス
オーディオ専門店エレックスTEL.:0284-64-7346 FAX: 0284-64-7347
〒326-0837足利市西新井町3495-2
営業時間:10:30〜20:30
オーディオお役立ち情報
ネットワークの作り方
始めに
スピーカーネットワークを自作するのは、部品さえ揃えば非常に簡単な回路です。
そのためアンプ製作に比べれば工作が容易で、簡単な半田付けしか出来ない初心者という方でもご安心下さい。
むしろマルチウエイの難しいのはユニットの選出であったり、クロスポイントが適正でない場合も多く、ネットワークを使用したにもかかわらず繋がりが悪かったりするのは、そのユニットの相性が悪い場合や、適正なクロスを達成できない場合が殆どです。
工作としてはとてもシンプルですが、アンプを変える以上に音が変わる要素も大きく、一度コツを掴むとその奥の深さを楽しむことも容易です。
前置きはさておき、スピーカーネットワークの作り方は様々有るのですが、一番基本的な、<1>の6dBタイプと<2>の12dBタイプを御紹介いたします。
基本的にはほとんどこちらの2点ベースでで間に合うはずです。
<1>6dBカットタイプネットワーク
6dBの一番簡単なネットワーク作成方です。
このタイプはフルレンジユニットや高域をカットしないで使用するウーハーなどに、ツイーターユニットを追加させる際に便利です。
ツイーター側にコンデンサー(ローカット)
ウーハー側にコイル(ハイカット)
それぞれ配線は各ユニットの+側の端子に直列つなぎをするだけです。

このタイプのメリットは、簡単に作れるのと費用が安く出来きる事、そしてシンプルな回路のメリットが有ります。それぞれの数値は計算で簡単に出て来ます。
計算式
C(コンデンサー値/単位マイクロF)
L(コイル値/単位mH)
パイ(円周率の3.14)
F(周波数)
R(対象のスピーカーユニットのオーム数)
C<単位マイクロF>=1÷2÷パイ÷F÷R×1000000=159000÷F÷R
L<単位mH>=R÷2÷パイ÷F×1000=159×R÷F
例1:ツイーターとウーハーが共に8オームで800Hzのクロスオーバーの時
C=159000÷800÷8=24.84・・・=25<マイクロF>
L=159×8÷800=1.59=1.6<mH>
例2:例1同じ設定で16オームのユニットである場合はコンデンサーは半分でコイルは2倍です。
C=25÷2=12.5<マイクロF>
L=1.6×2=3.2<mH>
例3:例1同じ設定で4オームのユニットである場合はコンデンサーは2倍でコイルは半分です。
C=25×2=50<マイクロF>
L=1.6÷2=0.8<mH>
例1.2.3の様に8オームの数値が解かれば特殊なオーム数で無いかぎり8オーム表から数値が出て来ます。
| 8オーム/コイルコンデンサー値/6dB | ||
| クロス周波数 | コイル値<mH> | コンデンサー値<マイクロF> |
| 200 | 6.4 | 99 |
| 250 | 5.1 | 80 |
| 300 | 4.2 | 66 |
| 350 | 3.6 | 57 |
| 400 | 3.0 | 50 |
| 500 | 2.5 | 40 |
| 600 | 2.0 | 33 |
| 700 | 1.7 | 28 |
| 800 | 1.6 | 25 |
| 1K | 1.2 | 20 |
| 1.2K | 1.1 | 17 |
| 1.5K | 0.85 | 13 |
| 2K | 0.64 | 9.9 |
| 3K | 0.42 | 6.6 |
| 4K | 0.30 | 5.0 |
| 5K | 0.25 | 4.0 |
| 6K | 0.20 | 3.3 |
| 7K | 0.17 | 2.8 |
| 8K | 0.16 | 2.5 |
| 10K | 0.13 | 2.0 |
保存用にどうぞ上記の表のGIFファイル(nwgraph6db.gif/7,889
Bytes)です。
<2>
12dBカットタイプネットワーク
6dBよりクロスカーブの肩特性を急激に落とすのが特徴で、またそれぞれのユニットのオーバーラップする帯域を少なくしますので、6dBよりも濁りのないすっきりとした音質傾向になります。
しかしハイカット、ローカット共にコイルコンデンサーが6dBに比べて並列に使う分コストも割高になります。
一般的なスピーカーシステムなどの場合、純正のネットワークではこちらが多く採用されています。
厳密にはクロスポイントの特性に合わせ、同じ12dBカットのネットワークにもいくつか種類があり、クロスポイントの音圧を重視したタイプ、クロスポイントのインピーダンスを重視したタイプなどもあるのですが、それぞれ一長一短の部分もあります。
しかしユニットの特性に合致した絶妙な乗数の選定で作られたネットワークの場合、マルチアンプなどでは出せない絶妙なマッチングを見せることもあるのです

計算式
Ch(ローカットコンデンサー値/単位マイクロF)
Cl(ハイカットコンデンサー値/単位マイクロF)
Lh(ローカットコイル値/単位mH)
Ll(ハイカットコイル値/単位mH)
パイ(円周率の3.14)
F(周波数)
R(対象のスピーカーユニットのオーム数)
Ch/Cl<単位マイクロF>=(ルート)2÷4÷パイ÷F÷R×1000000=113000÷F÷R
Lh/Ll<単位mH>=(ルート)2×R÷2÷パイ÷F×1000=225×R÷F
その他事項は6dBと同じです。
8オーム計算が16オーム時はコンデンサーは半分、コイルは2倍など同じです。その他に、対象、非対象等も有りますが、上記基本形のみでほとんど対応出来ます。
下記に周波数対応表を記載しておきますが、この乗数で作られたネットワークの場合、クロスポイントでピークが出たり、また音のオーバーラップが多くなりやすいため、結果として不明瞭な音になってしまう場合が多くあります。
そのためハイカットの場合は低い周波数へ、ローカットの場合は高い周波数へずらした値で組む方が繋がりが良い場合が多くあります。
| 8オーム/コイルコンデンサー値/12dB | ||
| クロス周波数 |
|
|
| 200 | 9.0 | 71 |
| 250 | 7.2 | 57 |
| 300 | 5.9 | 47 |
| 350 | 5.1 | 40 |
| 400 | 4.5 | 35 |
| 500 | 3.6 | 28 |
| 600 | 3.0 | 24 |
| 700 | 2.7 | 20 |
| 800 | 2.3 | 18 |
| 1K | 1.7 | 14 |
| 1.2K | 1.5 | 12 |
| 1.5K | 1.2 | 9.4 |
| 2K | 0.91 | 7.1 |
| 3K | 0.59 | 4.7 |
| 4K | 0.47 | 3.5 |
| 5K | 0.36 | 2.8 |
| 6K | 0.30 | 2.4 |
| 7K | 0.27 | 2.0 |
| 8K | 0.23 | 1.8 |
| 10K | 0.17 | 1.4 |
保存用にどうぞ上記の表のGIFファイル(nwgraph12db.gif/8,203
Bytes)です。
*製作にあたってのポイント
・コイルについて
クロースオーバー周波数が低くなるほどLの数値が大きくなるので、コイルの巻き数が増えます。
そのため周波数が低い設定の場合はコイルによる直流抵抗分が増えやすくなりますので、コイルの巻き数が少ない鉄芯入りコイルを使用し、周波数が高い設定なら歪みの少ない空芯コイルを使うのが理想的です。
実際使用するコイルによっても異なるのですが、おおよその目安としては1kHz程度以下の場合は鉄心入りを使うほうがレスポンス的にも有利です。
ただし空芯コイルの方が歪みも少ない面もあり、必ずしもこれが正解というわけではなく、使用するコイル次第という面もあります。
またユニットの特性にもよりますが、ウーハーやフルレンジにあえてコイルを付けない方法もあります。
その方がコイルによる影響を受けないためレスポンスの良いサウンドとなります。
箱もしくはボードに取付る際はしっかりと接着やネジ止めを行なうと音のたるみ感が少なくなります。
2ウエイや3ウエイのネットワークを組む場合、12dBのネットワークではコイルが2個以上使うので、昔学校で習ったようにフレミングの法則の影響でコイル同士が互いに磁束の干渉を起こしてしまうので、スペースの許す範囲で極力遠くに配置したり、コイルの角度も同じ方向を向けて並べないようにまちまちにするように注意が必要です。
・コンデンサーについて
コンデンサーは、特にコイルほどシビアなセッティングは要求されませんが、使用するコンデンサによって音が大きく影響を受け易い点もあり、出来るだけ音質的に優れたコンデンサを使用したほうがいいようです。
ネットワーク用として様々な種類のコンデンサが用意されていますので、高域などの乗数の小さな安価な物でテストして選別するのもひとつの方法です。
また固定方法はやはりコイル同様で、しっかり接着等で固定したほうが良いです。
・クロスオーバーの選定
ネットワークを作るうえで一番の悩みは、クロスポイントの周波数の選定です。
とりあえずは使うユニットの周波数特性のデータや使用例を信じるしかないのですが、ユニットに負荷の掛かった状態で何処がベストなのかは、実際に音を聞きながら調整するカットアンドトライしかありません。
またユニットの音質傾向を掴むために音を出す場合、ウーハーは問題有りませんが、ツイーターなどは低い周波数が入るとユニットを断線させてしまったり故障させてしまうので、必ず小さめのコンデンサを直列に繋いだ状態で確かめてください。。
とりあえずメーカー推奨のクロスオーバー周波数を目安につないでみます。
もしくはメーカー純正のネットワーク値を真似するのも良いでしょう。
もともと異質なユニット<口径、振動板質量、材質、構造、音圧、他>が同じ音色で鳴る事はありませんから、音を聞きながら判定してクロスポイントの周波数をずらしてみます。
コイルの場合、タップ式のコイルを使用すれば、一つのコイルで数種類の値のコイルを試す事も可能です。
コンデンサーは並列や直列でコンデンサを並列に足すと値が換えられるので簡単です。
上記周波数対応表はあくまでも目安となりますので、トゥイーターなどをシステムに付加する場合などは問題がないのですが、通常この乗数で組んだネットワークの場合、クロスポイントでの各ユニット間の音のオーバーラップが多くなり、結果としてクロスポイントに大きなピークが出る可能性があります。
そのためハイカットの場合は少し低めの値を目安に、またローカットは少し高めを目安に、それぞれクロス周波数をずらして組む方が音と繋がりが良い場合が多くなります。
例としては、ウーハーなどのネットワークの乗数を400Hz程度の乗数で作った場合、ミッドレンジのネットワークを500Hz〜700Hz程度の乗数で組むなどすると、実質的なクロスポイントが500Hz程度になる事もあります。
これはユニットの特性などにも大きく左右されてしまうので、どの程度が理想というのはありませんが、そのようなことも念頭に入れてネットワークを組まれてみるといいかもしれません。
・その他の調整
ユニットの前後位置のずれによる位相の違いや音圧の違いが、リスニングポイントで聞く音が大きく変化します。
6dBカットのネットワークの場合、振動板の位置が同じ位置と仮定しても位相が90度ずれてしまい、特12dBカットの場合位相が180度ずれます。
そのためユニットの結線をローとハイで+−を逆に結線したり、ユニットの前後位置などを調整させたりします。
また低域用ユニットに比較して高域用ユニットの音圧が高い場合が多く、聴感上高域が煩く聞こえる場合が多くあります。
その場合音圧を減衰させるためにアッテネーターなどを利用して音圧を下げますが、抵抗のみで作る固定式アッテネーターや、ボリュームのように調整するアッテネーター、ステップ式コイルを利用したアッテネーターなどがありますので、それぞれコストと音質が大きく変わりますので、求める音にあわせてセレクトしてください。
・インピーダンス補正回路
上記記載のような簡易的なネットワークを組む場合、ミッドレンジやハイレンジのユニットでは、コイルやコンデンサのクロスポイントの微調整だけで調節が可能なのですが、ウーハーなどローレンジユニットの場合、狙い通りのクロスオーバー周波数から大きくずれてしまう事が殆どです。
これはユニットの動的インピーダンスの変化の影響で、同じユニットを使用していても箱の形式や容量によっても大きく変化してしまい、そのため予定のクロスポイントより大きく高域側にずれ込んでしまうためです。
この影響はウーハーのクロスポイントがずれるだけではなく、その上に繋ぐミッドレンジまたはハイレンジまでその影響が及んでしまいます。
一般的に計算上から算出されただけの乗数でネットワークを作り上げても、結果的にうまく繋がらないというのはこの為です。
それをユニットが悪いからとか形式が違うからとあきらめる前に、一度インピーダンス補正回路を検討してみてください。
使用するのはユニットの公称インピーダンスと同じ値の抵抗と、ある程度の容量のコンデンサになります。
ネットワークを組んだ回路の後とスピーカーユニットの端子の前の間に入れるのですが、抵抗とコンデンサを直列に結線し、それを+と-に結線します。
イメージ的には、12dBカットのネットワークのウーハーに平行に繋げられているコンデンサと同じように結線する物で、そのコンデンサに直列に抵抗を付加した物と同じと考えてください。
その抵抗とコンデンサの繋ぐ極性ですが、抵抗の方が+側なのかコンデンサの方が+側なのかなどの決まりはありませんので、ネットワークとユニットの端子の間に結線してあれば問題ありません。
抵抗値はすぐに選定が出来ますが、コンデンサの容量はユニットの特性や箱の影響に左右されますので、一概にこの値というのは在りません。
厳密に言えばクロスポイントの周波数の動態抵抗値が、ユニットの公称インピーダンスを目安に、ネットワークの設定抵インピーダンスと同じなら問題ないのですが、コイルやコンデンサの値を微調整させてクロスポイントの肩特性を変化させた時などの調整にも利用できるのです。
おおよそネットワークのウーハーに平行に繋がれたコンデンサの値程度を、コンデンサの容量のスタートポイントの目安にしてもいいかもしれません。
BOXなどに入ったウーハーなどのネットワークを作る場合、インピーダンス補正回路は必修となる場合が殆どですので、調整用に安価なコンデンサや抵抗を用意しておくとよいでしょう。
・ネットワークの更なる追求
ネットワークは部品点数も少なく工作も容易ですが、スピーカーユニットの性質にも左右されるとはいえ、その音の変化は非常に大きい物です。
ネットワークに関しては、様々なオーディオ関連の教科書類にも紹介されており、その作り方や調整の仕方も様々な所で紹介されています。
もちろんここに書かれている内容を参考にされるのもひとつの方法ですが、実際ネットワークを手にしてみるとその奥の深さが実感できる世界でもあるのです。
カタログデーターが音の良し悪しにあまり関係ないように、測定データー上優秀なクロスをさせるネットワークが必ずしもいい音にはならないのも事実です。
またマルチアンプに代表されるチャンネルデバイダーを利用した場合、電気的な信号がきちんとクロスしていたとしても、ユニット自体の動態が必ずしも同じということもない場合もあり、ユニットの円滑な繋がりと一体感を出す場合、ネットワークの方が繋がりがいい場合もあるのです。
たとえばアルテック515Bのような軽量振動版に強力な磁気回路のユニットの場合、分割振動の減衰が起きずに中音域まで音を汚してしまい易いため、チャンネルデバイダーでカットしてもその減衰が収まらずにうまく繋がらない場合もあります。
そこで中音域を汚さないようにと低い周波数から早めに減衰させてしまえばいいのですが、そうなると今度はユニットのおいしい部分まで同時にカットしてしまう場合もあります。
そのような時、おいしい部分のクロスの肩特性にあえてピークを作り出したり、音を汚してしまい易い部分をきっちり減衰させるなど、ネットワークならではの醍醐味もあります。
追求すれば教科書にも載らない独自の手法が満載の世界なのですが、トゥイーターなどをフルレンジに繋ぐなど、簡単な所からはじめてみることも可能なのです。
システムを買い換えるのも一つの楽しみですが、ネットワークで理想の音を追求するのも、オーディオの楽しみのひとつでもあります。
乾電池と豆電球を繋ぐ様なシンプルな回路ですので、皆様の理想とする音楽の世界を見つけてください。
 |
 |
その他関連ページ |